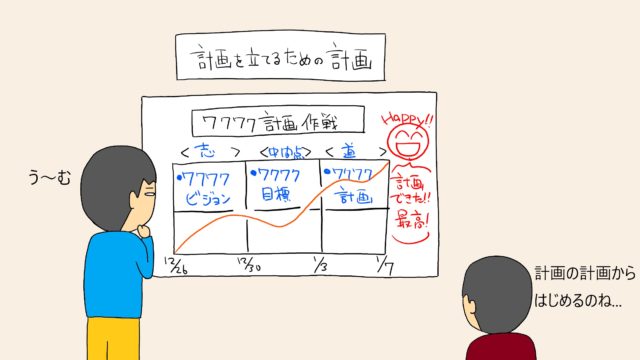「あの頃はよかった」
そう思ってしまう瞬間が、誰にでもあるのだと思う。たとえば、ぼくが「あの頃は」と強烈に思ったのは大学のころ。高校では毎日部活で野球をして、そこには自分が活躍できる場所があった。
練習がきついときもあったし、野球をつまらなく感じた時期もあった。それでもあの頃はとても恵まれていて、どんなに幸せな時間だったのだろうか。できればもう一度、いまの感情のまま、あの頃をやり直したい。そんなことを思っていた。
そんなふうに「あの頃」と思う場面は、その後も何度もあった。
大学を卒業したら「憧れの輝かしいキャンバス生活ではなかったけど、それを共有する仲間がいてよかった」と思うし、
会社に就職したら「大学院では研究は大変だったけど、尊敬する先輩と自由に研究できてよかった」と思う。
会社を退職してからも「閉塞感はあったけど、会社に人がいるってどんなにすばらしいことだったのか」と思っている自分がいる。
そしてこれからも折に触れて「あの頃は」なんて思うのだろう。きっと、いまのように動けることも、いまの自分の見た目も、いまの人間関係も貴重なのかもしれない。
1か月前、初めて入った定食屋さんの本棚に谷川俊太郎さんの詩集があり、料理が出てくるまでの時間に読んでみた。本のタイトルは忘れてしまったが、ひとつだけ覚えている詩がある。
『ときどき思う、死んでからヒトは、生きていたことが、生きているだけでどんなに幸せだったか悟るんじゃないかって。』
そうか、そうかもしれない。死んだらきっと、いまのようになにかを見ることも聞くことも触れることも、いまのように感じることも、なくなってしまうのかもしれない。
それならば、いま感じている焦りも、不安も、イライラも、ムカつきも、悲しみでさえも、幸せなことなのかもしれない。だったら思いっきり感じて味わってやろうじゃないかと、少し達観した気持ちで過ごせている。
「あるものを見る」というのは難しい。昨日あったものは今日もあり、明日もきっとあると考えてしまう。それが当たり前になり、失ってから初めて大事なものだったと気づく。これはもう、しょうがないのだろう。
あるものの大切さに気づくためには、それを失った未来を想像するしかない。けれど、その想像をひとりで深めることは難しい。だからこそ必要になるのが、他者の言葉だ。
他者の言葉に触れることで、私たちは初めて、自分が「いま」を生きていることを実感する。いまを生きる感覚というのは、人に触れてこそ生まれるものなのだ。